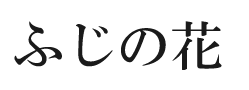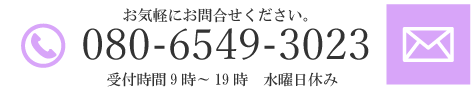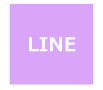皆様、こんにちは。本日は9/1(火)。「防災の日」です。この日は1923年の関東大震災に由来します。死者・行方不明者は10万人を超え、首都圏は壊滅的な被害を受けました。国はその教訓を後世に伝える為、また近代国家として体系的に「防災」を整備する為に「災害対策基本法」を制定しました。この法律は、国・自治体・事業者・地域住民それぞれに役割を与え、計画的に防災を行うための基盤となっています。しかし、制度が整備されても、それを活かすのは人です。そして…災害時、特に命が危険にさらされるのは高齢者や障害者です。移動に時間がかかる人、情報を理解しづらい人、薬や医療機器を必要とする人。こうした人々は災害時に「取り残されやすい」存在です。実際、阪神淡路大震災や東日本大震災の犠牲者の多くがご高齢者でした。つまり「制度=形」だけでは命は守れず、「人=心」が伴って初めて意味を持ちます。その中心にあるのが「気付き」と「寄り添い」なのではないかと思います。
この点に関係して…厚生労働省は介護分野における災害対応を強化しています。令和3年の介護保険法改正では、介護事業所に「業務継続計画(BCP)」の策定が義務化されました。停電や断水、職員不足などの非常時でも、可能な限りサービスを継続し、利用者の命と生活を守るための計画です。しかし、BCPはあくまで「枠組み」。現場で求められるのは、利用者一人ひとりへの細やかな気付きです。
例えば…
•車椅子を使う方には、避難所の段差を事前に確認しておく。
•認知症の方が環境変化で混乱しないよう、馴染みの毛布や写真を一緒に持参する。
•持病のある方には薬の予備をチェックしておく。
こうした寄り添いは、通知や法律の文章には書かれません。けれども実際には、それが利用者の命と尊厳を守る「最前線の防災」になるのではないでしょうか?
また…旧暦の9月は「長月(ながつき)」と呼ばれます。夜が長くなる「夜長月」の略とされる説が有力ですが、稲刈りを意味する「稲刈月」に由来する説もあります。いずれにせよ、日本人が自然の移ろいに敏感に気付き、それを言葉に託してきたことの表れとも言われております。
秋が深まるにつれ、人は静けさの中で自分や他者の存在を思いやります。災害や介護においても「気付き」と「寄り添い」が大切であることを、この季節の名が私たちに思い出させてくれるのではないかと思います。
更に…日本人の情緒溢れる心を映す古典文学の中で9月は、下記の様に…自然と人の心を映す豊かな題材となってきました。
・例えば…『徒然草』第137段。
『九月尽といふことは、いとをかし。九月尽に菊を折りて、人に贈るといふもをかし。』
9月の終わりを菊の花に託して人に贈る。そこには季節を惜しみ、人に寄り添う心が表れていると言われております。
・例えば…『新古今和歌集』
『村雨の 露もまだひぬ 槇の葉に 霧立ちのぼる 秋の夕暮れ』(藤原定家)
夕暮れに立ちのぼる霧と、人の心の寂寞とを重ねた歌。自然の小さな変化に気付くことが、深い人間理解へと繋がっていると評されております。
以上の様に…日本人の情緒溢れる心を記している古典の世界に触れると、当時の人々も「気付き」と「寄り添い」を大切にしていたことが見えて参ります。
9/1の『防災の日』に寄り添いつつも…
実際の介護現場に即した災害時の「気付き」の事例をあえて挙げてみますと…
•例1 【避難所での認知症の方への対応方法】
ある高齢女性は、避難所に到着すると環境の変化に混乱し、落ち着きを失いました。しかし、職員が「いつも家で座っている座布団」と「家族の写真」を持参したことで、次第に安心を取り戻しました。これは「環境の連続性」に気付いた支援が功を奏した例です。
•例2 【透析患者への対応方法】
災害で停電や断水が起こると、透析を必要とする方は命の危険にさらされます。ある地域では、日頃から自治体と医療機関、介護事業所が情報共有をしており、災害発生直後に代替の透析先を確保できました。普段の「連携への気付き」が救命につながったのです。
•例3【独居高齢者の安否確認】
豪雨災害の際、地域の民生委員が「毎朝同じ時間に洗濯物を干す姿が見えない」と気付き、訪問したところ、体調不良で動けなくなっていた独居高齢者を発見しました。これは地域の日常的な目配りが命を守った例です。
以上、これらは全て、「制度」ではなく「人の気付き」から生まれた寄り添いの実践です。
•災害対策基本法は社会を守る枠組みですが、実際の避難には地域住民の気付きが不可欠です。
•厚労省通知は介護施設の防災を進めますが、現場での寄り添いがなければ形骸化します。
•長月という言葉は、自然の移ろいに気付いた人々の感性から生まれました。
•古典文学も、人の心や自然の微細な変化に寄り添い、普遍的な真実を伝えてきました。
つまり「気付き」や「寄り添い」は、命を守るだけでなく、文化を育み、人のつながりを深める根源的な力へと進化する源となっているのではないでしょうか?
それ故に…これからの社会に必要なのは、法律や通知を「形式」として受け止めるのではなく、日常生活の中で些細な『気付き』と『寄り添い』を育む事ではないでしょうか?
例えば…
•家族と歩くときは、高齢者の歩幅に合わせる。
•地域の避難訓練で、車椅子や杖を実際に体験する。
•季節の移ろいを感じ、古典の言葉を通して思いを語り合う。
これらの行為は…小さな行為に思えるかもしれません。しかし、その積み重ねは非常時に命を守る大きな力になり得ます。
長月の夜長は、静けさの中で人と向き合い、寄り添う時間を与えてくれます。人の情緒溢れる心を映す古典の言葉は、現代に生きる私たちに「気付き」を思い出させます。
身近な人の変化を見逃さず、声をかけ、手を差し伸べること。それが、災害に強い社会を築き、人としての豊かさを育む事だと思います。
そして…その様に行い続けることが自分を含む地域社会との繋がりを豊かにして行き、日々の当たり前の日常を支える基盤にも繋がるのではないかと私は考えます。
今も尚、大変な想いを日々の日常の中で感じておられておりますご利用者様や、その様な方々を必死に支えておられますご家族様の何気ない日常の中で…その様な些細な『気付き』や『寄り添い』が積み重ねられます様に…『ふじの花』では微力ではございますが、裏から支える事ができます様に…そっと…お手伝いをさせて頂いております。