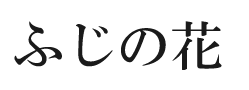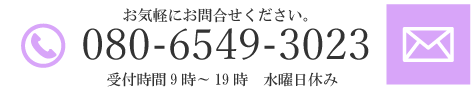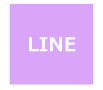皆様、こんにちは!本日は8/15(金)。今年は79回目の終戦の日です(玉音放送当日)。そして…日本がポツダム宣言の受諾を最終決定したのは、玉音放送の1日前、昭和20年(1945年)8月14日の正午過ぎのことだったとの事。昭和天皇(1901~89)の2度目の「聖断」でようやく決着したそうですが、玉音放送が流れるまでの1日間は、薄氷を踏むような状況が続いた様です。
作家の 半藤(はんどう)一利(かずとし)氏 (1930~2021)はその 顛末を克明に調べ、『日本のいちばん長い日』に記しています。「近現代は40年周期で興廃を繰り返す」という半藤氏の「40年史観」によると、明治38年(1905年)の日露戦争勝利で頂点に達した日本の軍事力が、落ちるところまで落ちたのが1945年の終戦の日だったとの事。
そして、昭和27年(1952年)に再独立した日本は、国の発展基盤を経済力に切り替え、40年後の平成4年(1992年)にバブル景気で経済的繁栄の頂点を迎えたと言われております。すると…今の日本はそこから40年続く没落のさなかにいることになります。
半藤氏は周期を40年とした理由を、「世代が入れ替わる期間が40年だから」と説明しています。だとすれば、悲惨な戦争を知る世代の入れ替えは、来年で2回目が終わる。悲惨な戦争を体験した世代だけでなく、その世代からじかに悲惨さを聞いた世代も、間もなく社会の中心から消えていく。半藤氏が玉音放送までの1日を調べ上げたのは、時代の節目の記録を引き継ぐことが、いずれ消えゆく世代の責務と考えていたからかもしれません。
万葉集には…
その編纂に携わった歌人として、大伴家持が挙げられますが、その歌の中に…
『ぬばたまの 夜は明けぬらし 白露の 置くこの庭に 鶏鳴くも』
という歌があります。
そのまま訳すと…
『夜は明けたらしい。白露に濡れている庭に鶏が鳴いている』という様な現代語訳になると思われます。これは人を鶏に例えて、その鶏がけたたましく鳴く姿で…やっと夜が明けてきた事を知った…という様な情景が感じられ、転じて、そこまでけたたましく鳴かなければ夜が明けた事もわからなかった…という歌として知られています。
半藤一利氏が1番言いたかった事は…いずれ消え行く世代の責務として『平和を語り継ぐ』事の大切さ、日々の当たり前を大切にする事だったのではないでしょうか?
世界の歴史を見ても、人間は悲しい事に忘れた頃にそれまで大切にしてきた心を無くして、正義の名の下に日々の当たり前を崩壊させて来ています。
そして…万葉集の大伴家持の歌にある様に…現在はその没落の最中におり、『鶏が鳴いている』状態になって…初めて周囲の状況に気付き始めているのかもしれません。
先の参議院選挙において、私達は国会議員として多くの方々を代表者に選びました。世界経済が変転流転する中にあって、自分の利益だけに囚われていると…やがて『鶏が鳴いている』状態になっていても、夜が明けている事に気付かずに…平和の大切さ、日々の当たり前の大切さを失う愚かな行為を行なってしまわないか…危惧しております。
8/15という終戦の日に当たって、はからずも若くしてこの世を去らなければならなかった人々とそのご家族の無念さを想う時、その様な無念さを今後の日本の歴史に残してはならないと…願わずにはいられません。
そして…
その様な無念さを継承してしまわない様に…
尚一層、人と人の琴線に触れる『気付き』に敏感になれる様に…そしてその『気付き』に『寄り添う』事ができます様に…日々の介護の現場においてもお支えして参りたいと強く思いました。