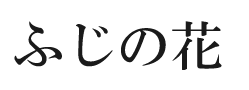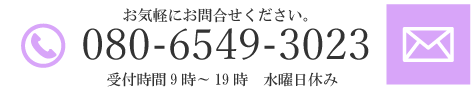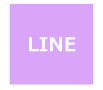皆様、こんにちは。本日は10/1。陰暦で『神無月』とも呼ばれる10月の最初の日。様々な記念日として登録されておりますが…『和の日』として、日本の文化、伝統を見つめ直し、調和、感謝、助け合い、譲り合いといった「和の精神」を広めることが目的として制定された日としても有名な日だとか。日付は10と1を「101」として人(1)と人(1)が和(輪=0)で結ばれる形であることと、神様が出雲に集まって平和について語り合う月(神無月=10月)の最初の日との意味から。多くの人々がこの日にお互いの幸せを祈り、和解する日にとの願いが込められている様です。記念日は2017年(平成29年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されたとの事です。昨今の世界情勢を思う時、感慨ひとしおと思われる方々もいらっしゃるのではないでしょうか?
さて…前回のブログでは…人は加齢に従い、自らの体調の変化や周囲の環境に合わせて、少しずつ自らのDNAも変化させて参りますが、考え方を改める事、つまり、加齢に従い数多くの失敗をしてもその失敗を将来への『意味付け』を行って、自己投資を行う事はできる事などを述べさせて頂きました。そこで本日はこの『失敗を将来への自己投資=意味付け』を①視点②視野③視座という観点から介護の現場に落とし込む…すなわち…特に認知症(失行・失語・失認など)に悩む方々へ贈る言葉として…どのように受け取って頂ければ良いのか?できる限り具体性を持たせて考察して参りたいと思います。
まず、失行、失語、失認についての具体的な言及は過去のブログ(6/7投稿の「血液の流れ方と認知症の3大症状(失行、失認、失語)との関係について」、5/24投稿の「薬の副作用がADLに与える影響について」など)をご覧になって頂けましたら幸いですが、もう一度おさらいをしたいと思います。
《失行・失語・失認とは何か》
•失行:体は動くのに、目的のある動作ができなくなる(例:服を着られない、歯ブラシを口に持っていけない)。
•失語:言葉の理解や発話が難しくなる(例:言いたいことが出てこない、人の言葉が理解しにくい)。
•失認:見えているのに「何を見ているか」がわからない(例:コップを見てもコップと認識できない)。
これらは脳の異なる部位の障害によって起こりますが、共通して「脳のネットワークの柔軟性が失われる」ことが背景にあります。この『脳のネットワークの柔軟性』を考察する事が認知症予防に繋がるのです。即ち、過去のブログ(9/6投稿の「思考の柔軟性について」、9/12投稿の「続『思考の柔軟性について』」)で述べているように、脳科学の研究では、「新しい体験に挑戦する」ことが脳の可塑性(新しい神経回路を作る力)を保つことが知られています。新しい環境 → 予想外の出来事や失敗が増える→それに対処する → 脳が新しいルートで問題解決を学ぶ→結果として → 脳内ネットワークが多様になり、失行・失語・失認の予防につながる。
例えるなら、脳は「道路網」です。毎日同じ道だけを使っていると、その道が通れなくなった時に行き詰まります。しかし新しい道を試し、失敗しながらも別ルートを見つけていれば、渋滞や事故のときも対応できる。この柔軟性が老化や認知症の防波堤になるのです。
それでは…「新しい環境への適応」と「失敗にどう対処するか」というテーマを『視点・視野・視座』という観点を駆使して認知症状に悩む人々はどのように考えて行けば良いのでしょうか?
《失敗への対処と3つの視点》
失敗にどう対処するかは、認知症予防の実践にも深く関わります。というのは…認知症に対する対応方法を誤ると…ご本人様の症状を更に悪化させるだけでなく、対応しているご家族様やその利害関係人すべての方々に少なからず影響をもたらす事になりかねないからです。
① 視点(物事をどう見るか)
•「できなかった」ではなく「新しいやり方を試した」と捉える。認知症予防では「難しいことに挑戦すること自体が脳を刺激している」と理解する。
② 視野(関係する人や状況を広く見る)
•自分だけでなく、家族や仲間と一緒に工夫する。例えば、料理が失敗しても笑い話にできれば、それ自体が会話や感情表現の訓練になり、失語や失認の予防に役立つ。
③ 視座(立場を変えて考える)
「失敗=悪いこと」ではなく「失敗=脳のトレーニングの機会」とみなし、人生のストーリーの一部に組み込む。また、子どもや若者のように「遊びの延長」で挑戦できれば、ストレスも少なく続けやすい。
このように…新しい課題に挑戦して行く事は結果として幸せを増やす効果を高めるだけでなく、下記のように科学的な根拠を持っております。
•神経可塑性(Neuroplasticity): 新しい課題に挑戦することで、脳はシナプス結合を強化し、新しい経路を作ります。これは失行や失語の進行を遅らせる要因となります
•認知予備力(Cognitive reserve): 様々な経験を積んだ人は、脳に多少のダメージがあっても、別の回路を使って機能を補いやすいことがわかっています。
•失敗経験と前頭前野の活性化: 失敗から学ぶとき、前頭前野が強く働きます。前頭前野は言語や行動の計画に関わるため、失語や失行予防に重要です。
以上の様に…
•失敗を避ける生活は一見安全でも、脳にとっては刺激が少なく老化を早める。また、失敗を重ねながら新しい環境に適応する人は、脳の回路を豊かに保ち、失行・失語・失認の予防につながる。即ち…
•失行予防
例:旅行先で切符を買う → 新しい機械の操作を学ぶ → 手と目を協調させる練習。道具の使い方に慣れることが「動作の地図」を脳に書き込み直すことにつながります。
•失語予防
例:新しい趣味の教室で友人と会話する → 知らない単語を聞く・話す → 言語野を活性化。言葉をアウトプット・インプットする機会が増えるほど脳は言語機能を保ちやすくなります。
•失認予防
例:知らない街で地図を見て歩く → 風景を認識して位置関係を把握する。新しいものを「見分けて理解する」ことが視覚認知機能のトレーニングになります。
つまり「環境の変化を受け入れること」=「脳を幅広く使うこと」なのです。そして、この「受け入れる」側の介護者側の姿勢そのものが…認知症を悪化させるか、維持させるかのターニングポイントである事を殆どの方が認知できていない事、即ち、介護の現場では…原因の中心人物=ご本人様ではないご家族様や介護者側の対応方法が問われる事が大きいのです。また…「視点」「視野」「視座」を切り替える事も介護者側の問題なのです。ご本人様の失敗を介護者側が前向きな体験に変えられるか?つまり、失敗は単なる「つまずき」ではなく、認知症予防のための大切な栄養素だと考えられるか?と問われているのです。この点は…過去のブログ(9/22投稿の『続々「思考の柔軟性」について』)で述べている通り、失敗の意味づけや扱い方(認知再評価、エラー許容の文化)が、介護者側の学習の伸びしろを左右します。つまり、ご本人様の失敗は“高価なデータ”ではありますが、介護者側の取り出し方次第で、毒にも薬にもなり得るという事です。「失敗」という出来事を、ただの後悔や痛みで終わらせず、そこから「気づき」や「新しい発想」へとつなげていく姿勢こそ、人を豊かにし、また介護や人生そのものに深みを与えてくれるのではないでしょうか?
人生に彩りを加え、より深みを増す事は並大抵の努力では成し遂げられません。そこには苦渋を舐めた経験があるからこその…唯一無二の『彩り』があるのではないでしょうか?