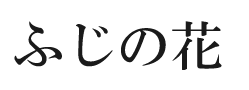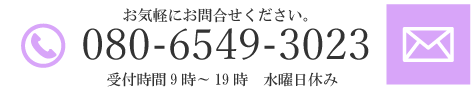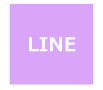皆様、こんにちは!本日は7/20(日)。日本では参議院選挙の投票日です。国内外の課題が山積されている現状の中で…私達はどの様な未来の日本を形作ろうとするのでしょうか?『どうせ投票したって、結果は同じでしょ!何の意味があるの?』『今までの与党である自公政権を支持した方が長期的な視野に立った政策が形作られる』『先ずは給与の手取りを増やすべく、社会保障費の削減に取り組み、人口減少から来る不安を取り除くべき』『一時的な手取りとはいえ、給付を頂ける事はやはり助かる』『トランプ政権が投げかけている関税にどの様に対応できるか?世界的な視野を持って対応して行くべきだ!』『トランプ政権に対してもNO!と言える日本であるべきだ!』『外国人政策を見直すべきだ!』『関税政策にも屈しない内需の拡大にシフトすべきだ!』等…多くの議論と公約が飛び交っております。
この点、介護人材を取り巻く課題は非常に厳しいモノがございます。2000年に介護保険制度が創設されて以降、わが国は高齢社会の進行とともに、数々の法改正と制度整備を行ってきました。
1.2000年:介護保険制度施行(介護保険法)
→介護を「家族の責任」から「社会の責任」へと転換。
2.2006年:介護職員処遇改善交付金の創設
→介護職員の賃金改善を図り、人材流出の抑制を目指す。
3.2012年:認知症介護基礎研修の義務化に向けた通知(段階的)→専門性を高めるための教育体制整備。
4.2015年:地域包括ケアシステムの推進と生活支援体制整備事業の開始→多職種協働のなかでの介護人材の再定義。
5.2019年:介護職への外国人受入れ拡大(技能実習制度・特定技能制度)→人手不足への即時対応策として、国際的人材導入。
6.2021年:介護職員等特定処遇改善加算の導入→経験・スキルに応じた賃金格差是正の仕組み。
7.2024〜2025年:ICT導入・介護ロボットの推進に関する実施計画の通知→人手不足対策としてのデジタル人材の必要性を強調。
このように、制度は絶えず改善され、厚生労働省も人材の処遇向上に力を注いでいます。しかし現実は厳しく、人口減少に伴い、介護の現場はますます人材不足に拍車がかかっています。
現場の声としてよく耳にするのが、「優秀な人材ほど辞めていく」という逆説的な状況です。なぜこのような現象が起こるのでしょうか?その背景には、「論理的な思考で現場を捉えられる人材が見落とされ、また育てられていない」という現実がある様に思われます。現場では即戦力や「とにかく動ける人材」が求められるあまり、長期的視点で現場を整える力、調和を重視する思考力を持つ人材を採用・育成する余裕がないのが現状です。その結果、「命令には従えるが、考える力のない人材」だけが残り、現場の停滞と過労が繰り返される構図が生まれているようにヒシヒシと感じます。
求められるのは、「思いやり」だけではありません。
むしろ「論理的な知恵を出し合い、協働の中で調和を築いていける力」がますます重要になるように感じます。そうした人材を見極めるためには、理数的素養を持つかどうかを、形式にとらわれず見抜く試みが必要です。
例えば、その方法として、私は一見すると小学生でも解けそうな形をとりつつも(実は高度な数学的・論理的思考を要する問題を用いて、どんな人でも採用する方法を採りながらも、その中から、上記問題を用いつつ)、リーダー層・中核人材を選抜していくことを1つの方法論として提案したいと思います。
理由は以下の点に挙げられます。
例えば…
問題①:図形の折り方
「この図形、あと何回折ると正方形になりますか?」
※空間認識力、論理的想像力が問われる。
問題②:ロウソクと時間測定
「1本10分で燃え尽きるロウソクが2本あります。15分を正確に測るにはどうしますか?」
※発想の柔軟性、順序の論理性が問われる。
問題③:数列の法則性
「1、2、4、7、11、? 次に来る数は?」
※数的推理、漸化式的理解が求められる。
問題④:人員配置と統計的感覚
「平均して3人に1人が月に1度お休みを取ります。今月10人の職員がいるとしたら、業務に支障が出ないための最少の人員配置は?」
※統計感覚と現場対応力が問われる。
問題⑤:握手の回数からの人数推定
「握手が合計45回行われた場合、参加者は最大何人?」
※組合せ理論、数的処理能力を試す問題。
上記の問題には…答えが何も1つとは限りません。また仮に1つであったとしてもそこに至る方法は幾つか考えられる可能性があります。この様に、現場指導や採用面談等で「柔軟な思考力・プロセスの多様性」を評価する事こそが『多くの課題を自分の利益や該当事業所の利益とは切り離した能力』を駆使できる人材を輩出して行き、一見遠回りに見えて、魅力ある人材の集まる点になるのではないかと考えます。そしてその様な考え方を行えば、いつしか点は線になり、線は面になり、面は多面体になり、多面体から3次元へ、3次元から様々な理数的な考え方のできる人材集積地となる様に考えます。
例えば…
私なら上記の例題から求められる答え方を以下の様に…作ります。
【問題①】図形の折り方
問題:この図形、あと何回折ると正方形になりますか?(※視覚情報を用いる問題のため、ここでは抽象的に解釈します)
想定される正解例(正方形に至る回数)
答え:あと1回(またはあと2回)
【導き方①(視覚的直感ルート)】
•すでに紙が1回折られており、形が正方形に近づいている
•端を揃えるように1回折るだけで正方形になる場合(あと1回)
【導き方②(幾何学的推理ルート)】
•折り目と辺の長さから、2回目の折りで中心を基準に対称に折る必要がある場合(あと2回)。※元の折りがずれている場合など、視覚的な補正を含む
【問題②】ロウソクで15分測る
問題:1本10分で燃え尽きるロウソクが2本。どうすれば15分を正確に測れるか?
答えは1つ(15分)だが、導き方は2通り
【導き方①(基本)】
1.1本目:両端に火をつける(5分で燃え尽きる)
2.同時に2本目:片側だけ火をつける
3.1本目が燃え尽きたら(5分経過)、2本目の反対側にも火をつける
4.残ったロウソクは5分で燃える → 合計15分
【導き方②(時間分割による思考)】
•10分間で1本すべて燃える
•両端に火をつけると、1/2の時間=5分で消える
•5分という単位を作り、それを2回繰り返す設計にすることで15分を作れる、と数理的に導き出す。
【問題③】数列の次の数字は?
問題:1、2、4、7、11、?
正解:16
【導き方①(差分を見る)】
•順に差をとると:+1 → +2 → +3 → +4 → +5
•次は……+5 → 16
【導き方②(一般式で求める)】
•項ごとの差が増えているので2次式と想定
•数列の差分から漸化式 aₙ = aₙ₋₁ + n と仮定し
→a₅=11 → a₆=11 + 5=16
【問題④】介護施設の最少配置は?
問題:3人に1人が月1で休む場合、10人全員が交代で休んでも業務が回るには?
答え:最低8人は常時必要
【導き方①(平均的欠勤を見積もる)】
•月に3人が休む(10人中3人)
•業務に支障が出ないためには、常時勤務者が7人必要なら、最低10人いれば回る。ただし突発休も考慮し、余裕を持って8人常勤必要。
【導き方②(週単位でモデル化)】
•1人の欠勤日数 ≒ 月1日
•10人で10日分欠勤
•月20営業日として、1日0.5人分欠ける想定
→ それを補完できる人員は8人以上
【問題⑤】握手の回数と人数
問題:全員が1回ずつ握手して、合計45回になるとき、参加者は何人?
答え:10人
【導き方①(組合せ公式)】
•n人で握手した回数は、n(n−1)/2
•これが45に等しい
→n(n−1)/2 = 45
→n(n−1) = 90
→n = 10
【導き方②(逆算と試行)】
•小さい数から順に試す:
6人 → 15回
7人 → 21回
8人 → 28回
9人 → 36回
10人 → 45回
■まとめ
これらの問題は、「計算が得意かどうか」ではなく、「現場にある多様な課題を数理的視点で整理し、解決策を導けるか」という力を測ることを目的としています。ここで言う『数理的視点』とは何か?
介護の現場では、毎日いろいろな出来事が起こります。たとえば…
•「今日は職員が少なくて対応が大変だった」
•「○○さんのご家族が急に来訪された」
•「同じ時間にトイレの介助が重なってしまった」こうした出来事の一つひとつは「個別の困りごと」ですが、それを「なんとなくの感覚」ではなく、『数字や順序、しくみとして整理すること』を「数理的な視点で整理する」と言います。もっとやさしく言うと…私たちはつい、「なんとなく忙しい」「なんとなく足りない」と思ってしまいます。でも、それを「なぜそうなるのか?」と考える力が、数理的な考え方です。たとえば…
【例1】
▶「1人の職員が1日で何人の方に対応しているのか?」
▶「時間帯ごとに何回、トイレ介助や食事介助が集中しているのか?」
▶「○人でシフトを組むと、何人の休みを確保できるのか?」
こういう風に、数字やルールで整理すると、改善のヒントが見つかりやすくなります。
介護という分野こそ、無限に拡がる人の心を感情に偏る事なく、上記の様な論理との両輪で支えられるべきと考えます。つまり、冷静な分析力と人間理解を両立できる人材こそ、これからの日本の介護を支え、AI時代にも斬り込んで行く人材育成となっていくのではないかと考えます。
7/20(日)という国政選挙の日に…様々な視点を感じ取りながらも…未来の日本を長期的に支える人材が輩出される事を願ってやみません。