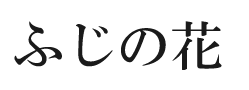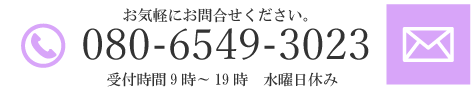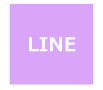皆様、こんにちは!本日は7/8(火)。昨日は七夕という事もあり、各地でお祭り等も開催されていたようです。7月7日の夜、織姫と彦星が年に一度、天の川で出会う…そんなロマンチックな物語は、子供達にとっての行事だけでなく、大人の心にもそっと響く何かがあります。そんな七夕伝説ですが…実際には…織姫はこと座の1等星・ベガで、彦星はわし座の1等星・アルタイルと言われています。七夕伝説によると、年に1度、7月7日の夜に会うことができる織姫と彦星ですが、星が実際に移動することはありません。2つの星の間は、14.4光年ほど離れていて、これは、光のスピードでも約14年半かかってしまう距離です。つまり、2人が光のスピードで移動したとしても、1年に1回会うことは、とても無理なのです。それでも…人々は果たせぬ夢を星になぞらえて『伝説』として…想いを次世代に託して行ったのでしょうね。そこには「待つ心」や「想いを伝えること」、「すれ違いの切なさ」といった、人の深い感情が込められています。それは、私たちが介護の場で出会う、一人ひとりの物語とも静かに重なりあうようにも思われます。
日本では古くから七夕が詠まれてきました。
例えば、『古今和歌集』に収められている…
『天の川 絶えぬ契りを たのみつつ 年に一度の 逢瀬をぞ待つ』(読み人知らず)
上記の詩歌は…
「天の川の流れが絶えることのないように、ふたりの縁も変わらぬものと信じながら、年に一度の出会いを心待ちにしている」…切なくも、あたたかい願いがこもった一首であり、目に見えぬ絆を信じて待つ心が表れていると言われております。これは、私達がが介護で関わる方々の想いや、言葉にならない願いにも通じるものがあります。
介護の現場でも、ご本人様の表情やしぐさ、わずかな変化に「気付く」こと、そしてその気付きに「寄り添う」ことが、もっとも大切な支えとなります。
たとえば…
•言葉にはされないけれど、ふと手を伸ばした先に「懐かしい何か」があることに気づく。
•普段より静かな表情の奥に、遠くの思い出が浮かんでいるのを感じる。
そんなとき、私達ができるのは、そばに座ってその想いに耳を傾けること、その沈黙を共有することです。これはまさに、年に一度、星空の下で2人がそっと寄り添う七夕の光景のようではないでしょうか。
七夕の夜、短冊に願いを書いて笹に結ぶという風習があります。これは単なる願かけではなく、自分の心に向き合う行為でもあります。介護の場においても、「あなたはどんな事をお願いしたいですか?」という問い掛けをご本人様に行う事がございますが…これはご本人様の尊厳を大切にし、その人らしさを引き出す大切なきっかけになります。
例えば、「昔のように畑を歩きたい」「孫と話せたらうれしい」といった願いは、その方の人生の記憶や希望とつながっているからこそ、それに『気付いて』、共に願うことが、何よりの『寄り添い』になります。
七夕の詩歌は、表には出てこない「心の奥の声」に目を向けるものです。そこには、誰かを想う気持ちと、そっと寄り添うやさしさがあります。
介護もまた、表情の裏にある言葉にならない願いに気付き、「その人らしさ」という星を見つけ出し、それに心を重ねることだと言えるのではないでしょうか?
七夕の夜、空を見上げるとき、人は皆、少しだけ静かになります。そして、自分の心と、誰かの心にそっと触れようとします。
介護の場でもまた、そうした「静かな気付き」や「そっと寄り添う姿勢」が、その方の命の物語を照らす灯(ともしび)になるのではないでしょうか?
『ふじの花』では…人と人とが出会い、繋がる奇跡を重んじ、その裏に隠された様々な想いをご関係者の皆様と考え、その繋がりを大切に紡いで行くお手伝いをさせて頂いております。
今日もまた、日々ご自身の体調不良で大変な想いをされておりますご利用者様、そしてそのような方々を必死にお支えになられておられますご家族様にとって…少しでも心安らかな日々になる事ができますようにと…切に願いを込めて天の川に拝礼をさせて頂きました。