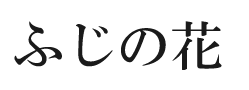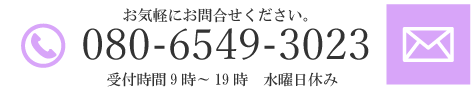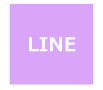皆様、こんにちは。本日は6/20(金)。まだ梅雨明けもされていないのに…気温が37℃近くにもなり、ニュースによると救急搬送された人々が数多くいたとか。数分間日光を浴びただけで汗びっしょりになってしまいました。汗をかく事は本来、体温を下げる効果があり、良いはずなのに不快な想いをしなければいけません。その理由は、調べてみると…①汗の蒸発が追いつかない為②ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラル(電解質)も出て、脱水症状や筋肉のけいれん等が起こる為との事。前回までのブログにも何度も挙げましたが、人の臓器の精密さは驚くばかりですが、その精密な体内環境を持ってしても追いつかない急激な自然の変化。救急搬送されないように前もって水分を多めに摂取する等の予防をとりたいものですね。
さて、本日も…皆様からのご意見を頂戴致しましたので、それに可能な限り寄り添い、お答えする形で述べさせて頂ければ…と思い、筆を取りました。それは…『前回のブログで、社会的に評価の高い実践例を挙げて頂きとても勉強になりましたが、その実践例を行う事で前々回まで述べていた身体の各臓器(心臓・腎臓・肺・膵臓・肝臓・胃・神経・血液)は①何故良い効果があるのか?更に②どんな変化が期待できるのか?』というご質問でした。今回は私なりに社会的に評価の高いご意見を調べた上で、このご質問に答えて参りたいと思います。
1. 心臓(循環器)への効果
①どうして効果があるのか?
•有酸素運動や適度な歩行は、心臓の筋肉を強くし、心拍リズムを安定させます。
•ストレス軽減や睡眠改善により、自律神経のバランスが取れて心拍数が整います。
②どんな変化が期待できるのか?
•血圧が安定し、動悸や息切れが軽減。
•心不全の進行予防。
•血管の柔軟性が保たれ、動脈硬化の予防につながります。
2. 腎臓(ろ過・水分バランス)への効果
①どうして効果があるのか?
•水分摂取や食生活の改善によって、老廃物がスムーズに排出されやすくなる。
•血圧のコントロールや血液の質が改善することで、腎臓への負担が減少する。
②どんな変化が期待できるのか?
•尿量や尿成分のバランスが整う。
•浮腫(むくみ)の軽減。
•腎機能の悪化スピードが遅くなる。
3. 肺(呼吸器)への効果
①どうして効果があるのか?
•軽い運動・呼吸法(腹式呼吸など)により、肺活量が保たれる。
•歌や会話、音楽療法も自然な呼吸訓練になります。
②どんな変化が期待できるのか?
•酸素取り込み効率の向上 → 血中酸素濃度が安定。
•咳・痰の出やすさ改善、誤嚥性肺炎の予防にもなります。
•活力や集中力の維持。
4. 膵臓(血糖コントロール)への効果
①どうして効果があるのか?
•食事の見直し(糖質・脂質のバランス)、適度な運動により、インスリンの働きがサポートされます。
•ストレスを減らすことで、血糖値の急変を防ぎます。
②どんな変化が期待できるのか?
•高血糖・低血糖の波が減り、糖尿病悪化を予防。
•すい炎や膵機能低下のリスク軽減。
5. 肝臓(解毒・代謝)への効果
①どうして効果があるのか?
•食生活の改善で、脂肪肝や高アンモニア血症の原因となる物質を減らせます。
•規則正しい生活リズムは、肝臓の再生能力を助けます。
②どんな変化が期待できるのか?
•肝機能値(AST, ALTなど)が安定。
•疲労感の軽減や食欲の回復。
•薬の代謝も円滑に進みやすくなる。
6. 胃(消化)への効果
①どうして効果があるのか?
•ストレスが軽減すると胃酸の分泌が正常化。
•食欲を引き出す工夫(五感刺激)により、胃の運動が促されます。
②どんな変化が期待できるのか?
•胃もたれ、便秘、下痢の改善。
•食事量・栄養バランスが整い、全身の栄養状態も良くなります。
7. 脳(神経系[中枢神経・自律神経])への効果
①どうして効果があるのか?
•認知刺激や感情表現(回想法・会話・音楽)は、前頭葉・側頭葉(大脳の左右両側面に位置する脳の領域で、主に聴覚、記憶、言語理解、視覚認識などを司さどるとされています)・扁桃体(側頭葉の内側の構造であり、大脳辺縁系とよばれる情動に関連する回路の主要な構成要素の1つ。 特に恐怖や不安といったマイナスの情動に深く関わっている部分と言われる。)等に良い影響を与えるとされています。
•睡眠・生活リズムの改善は自律神経の安定に不可欠。
②どんな変化が期待できるのか?
•判断力・記憶力・行動意欲の改善。
•不安・イライラ・不眠の軽減。
•認知症の進行予防や失行・失語の悪化防止。
8. 血液・血流(循環)への効果
①どうして効果があるのか?
•運動・栄養・睡眠によって、血液がサラサラになり、流れやすくなります。
②どんな変化が期待できるのか?
•高血圧・動脈硬化・血栓のリスクが低下。
•貧血の改善、脳や心臓への酸素供給の安定。
•認知機能や体力の維持に直結。
以上、1〜8ような社会的に評価の高い知見がございました。主治医の先生、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の諸々の各専門家ともよくお話し合いの末にご参考になさって頂けましたら幸いでございます。
『ふじの花』では…日頃の皆様からの、体に関係するちょっとした疑問にお答えする形で…目に見える現象が、実はこんなにも様々な理由から導き出されて…今に至っている事を【納得】して頂くお手伝いをさせて頂いております。私も身体の事は素人ではありますが、だからこそより皆様の視線に寄り添える在り方を日頃から模索し、難しい身体の内部に関係する科学的な知見を調べる努力を行っております。そしてその『難しい知見』を『解り易く』お伝えする努力を行っております。そのような裏から支える存在として、今後ともお手伝いをさせて頂けましたら幸いでございます。