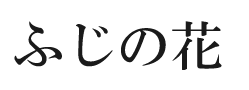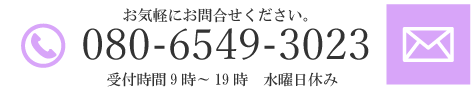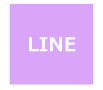皆様、こんにちは!本日は9/22(月)。前回は思考の柔軟性を推し進めて行くと…自らのDNAの変革の可能性に辿り着き、『心の持ち方や日々の選択が身体そのものを作り変えて行く』事になる事を述べさせて頂きました。しかし前回から数日経ったある日に、あるご利用者様のご家族様より…『上記の「新しい環境の変化に適応する」人は長寿で幸福度も高いが、反面慣れない環境の下で失敗も多いと思います。私自身も過去に様々な慣れない環境の中でどうしたら良い選択ができるか?悩んだ数々の可能性があり、そんな経験を積まない選択をしなければ良かったのにと…悔やんだ事が数多くあります。』というご意見がございました。確かにご家族様のご意見は経験に基づいた地に足のついた素晴らしいご意見であり、至極もっともな意見であります。この点、皆様はどのように思われますでしょうか?
そこで今回はこの失敗に対する対処方法としてどうしたら良いか?を考察をしてみたいと思います。というのは…この問題を論じる事が私が仕事として行っている介護を考察する事の助けにもなるのではないかと思ったからであります。以下検討致します。
まず…なぜ“新しい環境”は失敗を増やすのでしょうか?(でも価値があると思えるのでしょうか?)
•脳は「予測誤差」(思ったのと違った!)を学習の燃料にします。予測誤差が大きい状況ほど、線条体—前頭前野—ドーパミン系が学習更新を強め、行動戦略を素早くチューニングします(報酬学習理論)。
•ただし新奇環境はストレス反応も誘発し、注意が狭まりやすい。この点に一般的に人が後悔する境界線があります。ところが…ここでの失敗の意味づけや扱い方(認知再評価、エラー許容の文化)が、学習の伸びしろを左右します。つまり、失敗は“高価なデータ”ではありますが、取り出し方次第で、毒にも薬にもなり得るという事です。
言い換えますと…人間の脳は、新しいことに挑戦すると「ドーパミン」という意欲や学びを支える物質を分泌します。このドーパミンは脳の海馬や前頭前野を刺激して「記憶力」や「柔軟な発想力」を保つ働きがあるため、挑戦する人ほど老化がゆるやかになりやすいことが研究で分かっています。但し、新しいことに挑戦すれば当然「失敗」も増えます。たとえば…
•新しいスポーツを始めてケガをする
•新しい人間関係に踏み込んで誤解を招く
•新しい仕事のやり方を試して成果が出ない
これは避けられない現象です。つまり「挑戦=失敗の可能性」なのです。ここで大切になるのが、失敗をどう「捉え直すか」です。
結論から申しますと…失敗に対して様々な視点、視野、視座を分けながら進むべき方向性を見極める事が心理学・神経科学・行動科学の知見にも噛み合うのではないかと考えております。どういうことか?以下ご説明致します。
① 視点(短期的・個別の見方)
→失敗したその瞬間にどう感じるか、どう対処するかという視点。例えば…「新しい料理を作って失敗した 」事があれば、 より美味しくする為に「次は調味料を減らして(増やして)みよう」と考えを別の視点から前向きにできるし、更に「新しい人に断られた 」事があれば、そうならない為に 「話し方を変えてみよう」と考え方を変える事もできます。
上記のように…小さな修正を繰り返すことで脳が「誤りから学ぶ回路(エラーモニタリング)」を強化し、柔軟な対応力がつくことが分かっています。
② 視野(中期的・広めの見方)
→失敗を個別ではなく全体の中で捉える。例えば…料理で10回失敗しても、20回目で得意料理ができたら大成功。更に、仕事でアイデアが通らなくても、その経験が次の提案に活きる。等とより長期的な見方をする事もできます。心理学では「リフレーミング(枠組みを変える)」と呼ばれます。これができる人はストレスホルモン(コルチゾール)が下がり、長期的に健康にも有利だと報告されています。
③ 視座(長期的・人生全体の見方)
→失敗を「自分の成長や人生の物語の一部」として捉える。例えば…転職で失敗しても「挑戦したからこそ次の道に出会えた」。また、恋愛でうまくいかなかったことが「人間関係の深さを学ぶきっかけになった」。等…この「失敗を人生の意味づけに組み込める力」は心理学で「レジリエンス(心の回復力)」と呼ばれ、長寿や幸福度と強く関係することが研究で示されています。
以上のように…
•新しいことに挑戦する人は脳を若々しく保ちやすいが、その分失敗も多い
•失敗を「視点・視野・視座」で捉え直すと、学びと幸福につながる
•特に「失敗も含めて人生の物語」として意味づけできる人は、ストレスに強く、長寿や幸福度が高い
つまり、「失敗をどう解釈するか」が健康と幸せを大きく左右します。失敗を「傷」として残すのではなく、「経験の宝石」として磨いていける人が、本当に老化しにくく、人生を楽しめるのだと科学は教えてくれているように思います。
如何でしたでしょうか?
人は加齢に従い、自らの体調の変化や周囲の環境に合わせて、少しずつ自らのDNAも変化させて参りますが、考え方を改める事、つまり、加齢に従い数多くの失敗をしてもその失敗を将来への『意味付け』を行って、自己投資を行う事はできます。そして『失敗を将来への自己投資=意味付け』を①視点②視野③視座という観点から介護の現場に落とし込むと…より効果的になると…私は考えております。次回はこの点をより深く考察してみたいと思います。
今も尚、様々な疾患や認知症状で悩んでおられるご利用者様やそのようなご利用者様を真剣に支えておられますご家族様にとって…少しでも安心・安全な日々が参られますように…その想いに『気付き』『寄り添い』ながら…そっと裏から支える事ができましたら幸いでございます。