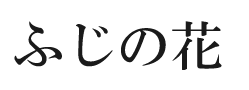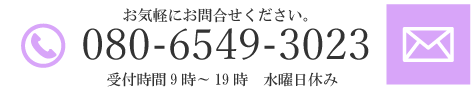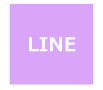皆様、こんにちは。本日は9/12(金)。前回は『思考の柔軟性』について…科学的な検証を踏まえた上で(老いる事がイケナイ事の様に述べる見解に対して…反対意見を検証しながら)…人は何歳になられても老いと共存しながら幸せな日々を暮らす事こそが大事である事を述べました。
では…この点を介護現場に置き換えるとどのように考えられるのでしょうか?
元気で好奇心旺盛なご利用者様は、脳のドーパミン神経が比較的保たれている可能性が高い。但し、その行動力自体が脳の活性化を維持する事も事実です。この場合に…介護者としてできることは、「すでに活動的な方」には、それを尊重して継続できるよう支え、「意欲が低下している方」には、小さな楽しみや人との関わりを通じて脳の活性を促す。つまり「その人の今の脳機能に合わせた環境づくり」が大切になるのではないでしょうか?
更に前回は「自由が頑固に変わる」場合の思考方法について検証を行い、「好き勝手する=本当の自由」ではなく、こだわりが強くなると逆に不自由になるとも述べました。この点を介護現場に落とし込むと…例えば…「私は絶対にこの椅子じゃなきゃ嫌だ」と言い張るご利用者様もいらっしゃいます。「若い頃はこうだった」と過去に固執する方もいらっしゃいます。更に「この食事は嫌い」と頑なに拒否する方もいらっしゃいます。これらは頑固さ(認知の硬直化)とも言える状態であり、柔軟性を失った「自由」と言えるのではないでしょうか?結果的に生活の選択肢を狭め、孤立や不満を深めることに繋がります。この場合、介護者としては、ご利用者様の「こだわり」を頭ごなしに否定せず、「別のやり方も試してみませんか?」と柔軟に促す工夫が求めたりする事が求められます。更に、例えば…食事で嫌いなものがあれば「味つけを少し変える」「小さな一口だけの挑戦」など代替案を示すことで、「頑固さの壁」を少しずつ緩められることも求められます。
この様な「心理的柔軟性」が幸福度・健康・認知機能維持に結びつくことが心理学では既に判明している事を述べました。
介護現場では、この柔軟さを引き出す工夫…例えば①小さな新しい体験を勧める事(季節の花を一緒に見に行ったり、新しい歌を一緒に聴いたり、初めてのレクリエーションに誘ったりする事など)により脳の可塑性を保ち、生活に彩りをご与えたり、②比較ではなく共感を重視する事(「昔はできたのに、今はできない」と嘆く方に対しては、「今はこの形で楽しめますね」と共感しながら別の方法を提案する事)により人と比べる不自由から解放され、自己受容を促したり、③頑固さを尊重しつつ緩める事(「私は昔から○○しか食べない」と言われたら…「○○が好きなのですね。じゃあ今日は少しだけ□□も添えてみましょうか」と、選択肢を広げて行く事)等の各種方法を勧める事により…ご利用者様に「老いを超えた豊かさ」をご提供する事こそが重要なのではないでしょうか?つまり…大事な事は…介護者が寄り添いながら「柔軟さ」を引き出す事、その工夫を考え出す事により、老いそのものを楽しめるようにする事ではないでしょうか?その様に…介護は「長生きそのものを目指す」のではなく、「その人らしい柔軟な生き方を支えること」が大事だと…考えられます。
しかし、実際の介護現場では…ご利用者様の条件によっては…認知状態が周囲の予想を超えて、ご家族様との関係も様々なご状態に変化する事もございます。ですが…いずれの条件や状態に至ったとしても…そこに至る過程に『気付く』か否か、そしてその『気付き』に『寄り添う』事ができるか否かという事こそが…人間の持つ『脳の可塑性』を生かし、老いと柔軟に寄り添う唯一の方法ではないかと思います。
そしてこの様に考えて行く事は…
自分自身のDNAの表現(エピジェネティクス)=変革の可能性 にも影響することが研究で示されつつあります。思考の柔軟さ・行動の多様さは、遺伝子のスイッチを「オン・オフ」する環境要因となり、老化のスピードや回復力にまで影響する可能性があるのです。そして、「心の持ち方や日々の選択が、身体そのものを作り変えていく」事になるのです。
故に…皆様が日々悩んでおられる事は…老いに対する人の自然な行為であり、何ら恥じる事ではない事をお伝えしたいと思います。