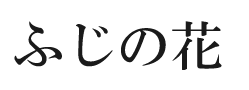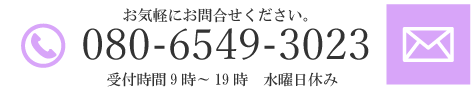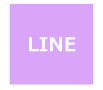皆様、こんにちは!本日は5/5(月)。子供の日🎏です。川沿いには今も尚、昔ながらの子供の成長を願う、鯉のぼりの季節感溢れる風景を見かける事がございます。表題の新古今和歌集の歌も古の人々が感じた想いを表出した表れではないでしょうか?
5月ともなると、初夏の陽気に包まれ、街角にはツツジがまるで炎のように咲き誇ります。その花々に誘われるように、蝶や蜂、小さな昆虫たちがひらひらと舞い、今日も命の営みが繰り返されています。植物はただ咲くだけでなく、花粉を媒介する虫たちを引き寄せる役割を果たし、更にまた、その虫たちはさらに他の命を支える存在となる。こうした小さな循環が、私たちの暮らしを静かに支えてくれているのだと思うと、不思議と心が和らぎます。
さて、今回は、ご利用者様の中で多い、脳血管障害の後遺症により言葉が出にくくなったり、食べることが難しくなったりしているご利用者様と日々向き合っておられるご家族様へ、少しだけ医学的な視点も交えてお話をさせて頂けましたらと思い、筆を取りました。
① 言葉にならない「伝えたい気持ち」
脳卒中などの影響で、言葉をうまく発することができなくなる「失語症」や、思うように発声できない「構音障害」は、周囲が見落としがちな苦しみです。「声にできない」ことは、ただの“沈黙”ではなく、たくさんの思いが内に詰まった“叫び”でもあります。たとえ発語が難しくとも、まなざし、手の動き、呼吸の変化――それらすべてが心の声の表現です。ご家族様が日々「伝えようとする努力」に耳を澄ませておられる姿には、深く胸を打たれます。リハビリの現場では、絵カードやジェスチャー、視線入力などを活用して「非言語的なコミュニケーション」を支える工夫が進んでいます。どれも、「できること」を見つけて伸ばしていくという視点が根底にあります。
② 食べることは生きること
嚥下機能の低下もまた、脳血管障害の後遺症として多くみられます。誤嚥(食べ物や飲み物が気道に入ってしまうこと)による肺炎のリスクを避けるために、食事を制限せざるを得ないこともあるかもしれません。けれど、「口から食べたい」という気持ちは、生きる力に直結しています。今は難しくとも、口腔体操や嚥下リハビリによって、少しずつ飲み込む力が戻ってくることもあります。食事の前に「深呼吸をひとつ」してから顔や首の筋肉をやさしくマッサージするだけでも、身体は確かに応えてくれます。嚥下の評価には、医師や言語聴覚士による「嚥下内視鏡検査」などの科学的な方法もあります。専門職との連携で、無理なく安全に、「その方らしい食事」を守る工夫ができます。
③ 季節と共に、小さな光を見つける
過去にご利用者様の外出支援において、口元にツツジの花を近づけたとき、微かに目を細めた瞬間がありました。その視線の先には、花に集まる小さな蝶が舞っていました。言葉にはならないけれど、そこにはたしかに「見ている」「感じている」感覚があったのではないでしょうか?
表題に掲げた古の歌が詠むように、「自然」はいつも、私たちの暮らしのすぐそばにあります。言葉では伝えきれない思いも、風や光の中で、そっと癒されていくのかもしれません。そして、命の循環を支える自然のように、ご家族様の存在も、ご利用者様にとっては大きな支えとなっているのではないでしょうか。どうか、ご自身のお身体も、季節と共にゆっくりと整えて頂く事が、回りまわってご利用者様の生き甲斐を支える元になると思います。
介護は、続けるほどに深く、やさしさを問いかけられる営みです。そしてその道のりを、科学知見に裏打ちされた情報に基づきながらも、孤独な介護に陥る事なく、「誰かと共に歩んでいる」と感じて頂けましたら幸いです。これからも、季節の移ろいと共に、そっと寄り添う想いをお届けする事ができましたら幸いでございます。