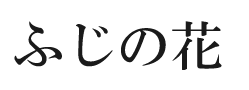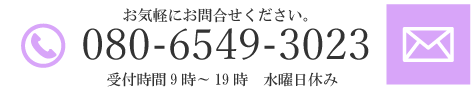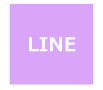皆様、こんにちは!本日は5/21(水)。季節の変わり目で気温の寒暖差とジメジメとした湿度に…体調を崩しやすい時期となっております。毎日の体調に気を遣いながら…皆様がどうかご無理をなさらないで…と願う日々が続いております。
先日、仕事で伺っているご利用者様のお庭の池に…小さな蓮の花の蕾がなっているのを見かけました。蓮の花は、泥水の中から茎を伸ばし、やがて清らかな花を咲かせる植物です。その姿は、『泥中の蓮(でいちゅうのれん)』という言葉にもあるように、どんなに濁った環境の中でも清く、美しく生きることの象徴とされています。清らかさ、尊さ、そして何より「諦めずに花を咲かせる力強さ」。それが、蓮という花が私たちに示唆する心ではないでしょうか?
そして…蓮の花言葉には、「清らかな心」「沈着」「救済」等があります。これらの言葉は、日々大変な想いをされている…ご利用者様やご家族様の心に、そっと寄り添うものではないでしょうか?介護の現場では、目に見える疲れだけでなく、心の奥に積もる想いや葛藤があります。思うように動かない身体への苛立ち、過去の自分との距離、そして誰かに頼ることの戸惑いや、支える側の心の消耗…。そんな日々の中では、自分の気持ちに蓋をしてしまうこともあるかもしれません。しかし、どれだけ泥にまみれても、その泥がなければ咲かない花があることを…蓮の花は教えてくれている様な気がします。つまり、苦しみや困難の中にこそ、生まれる美しさがあるのだということを…。
『蓮の露も いとど涙に 見えわたる
心のうちや 水のながれを』
室町時代の連歌師・宗祇のこの一句には、蓮の葉に宿る一滴の露を、こぼれる涙と見立てた繊細な眼差しが込められていると言われています。静かな水面に浮かぶ蓮の花の蕾と、そこに宿る露。その光景は、私たちの心の深いところに触れるような、何物にも代え難い…凛とした美しさを湛えています。
「もう限界かもしれない」「どうしてこんなに毎日辛い想いをしなければいけないの?」…そんなふうに思う日があっても…どうか心の中に、小さな蓮の蕾があることを思い出して下さい。蓮は、一夜にして咲くのではありません。水の底で…見えないところでゆっくりと準備をし、ようやく水面に顔を出し、ある朝、静かに花を開きます。皆様が歩んで来られた人生もまた…表からは見えない深い意味と価値に満ちているのではないでしょうか?
介護という営みは、ただお世話をすることではありません。そこには、見つめ合うこと、受け入れ合うこと、そして「今を共に生きる」という深い意味があります。時にぶつかり、すれ違い、涙をこぼすこともあるかもしれません。けれど、その涙もまた…蓮の葉に宿る露のように、光に照らされて美しく輝くときがあるのではないでしょうか?
〜〜蓮の露も いとど涙に 見えわたる〜〜
蓮の花は、派手さこそありませんが、静かに人の心を包む力があります。誰にも言えない苦しみ、積み重なる疲れ、言葉にできない思い…そうしたものすべてが、無駄ではないこと。泥の中からしか咲かない花があるという事…私達の周囲には…そのような示唆に富む姿がそっと…横たわっている事を気付かせて頂けます。
ジメジメとした日々が続いてはおりますが…『ふじの花』では…皆様の心の中に確かに存在する、何物にも代え難い『蓮の露』を見つけ出し…裏からそっと寄り添う存在であり続けたいと思っております。