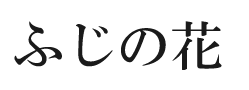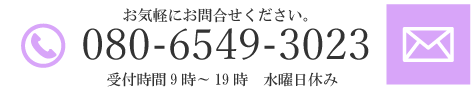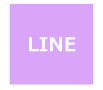皆様、こんにちは!本日は8/1(金)。今年も早くも8月になりました。8月の旧暦は「葉月(はづき)」と呼ばれています。「葉月」という名前の由来は諸説ありますが、最も有力とされているのが、
「葉落ち月(はおちづき)」が転じたもの
という説です。
秋が深まっていく旧暦8月(現在の暦でいうと、9月中旬から10月上旬にあたることもあります)は、木々の葉が色づき始め、やがて落ちていく時期です。そこから、葉が落ちる月、「葉落ち月(はおちづき)」と呼ばれ、それが縮まって「葉月」になったといわれています。
『枕草子』(清少納言)にも、秋の風物を感じる場面があります。
『秋は夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへあはれなり。』
ここでは、秋の夕暮れに鳥たちがねぐらに帰っていく様子が描かれています。木の葉が色づいていく中、静かに季節が進んでいく風景。まさに「葉月」の心を感じる場面です。
『万葉集』の中にも、葉が落ちゆく秋の情景を詠んだ歌があります。
『秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ
わが衣手は 露にぬれつつ(巻一・天智天皇)』
ここで詠まれているのは、秋の田に立つ仮小屋の屋根から露が落ち、袖が濡れていくという情景です。秋の深まりとともに、草木も朝露に包まれ、やがて葉が散っていく様子が目に浮かびます。こうした自然の変化に敏感だった古代の人々の感性が、「葉月」という名に込められているのです。
旧暦の「葉月」は、現代でいうと9月ごろ。夏が終わり、秋の気配が深まっていくこの時期は、
•虫の声が聞こえ始める
•空が高くなる
•朝夕の風が涼しくなる
•稲穂が頭を垂れ始める
そんな季節です。
木の葉が色づき、風に揺られて落ちていく様子は、「もののあはれ(哀れ)」を感じる日本人の感性に深く根ざしており、「葉月」という名にその心が宿っているとも言えるのではないでしょうか?
以上の様に…「葉月」は、ただの月名ではありません。そこには、
•自然の移ろいを見つめるまなざし
•命の終わりと再生を静かに受け入れる心
•四季を繊細に感じ取る日本人の感性
が込められています。
私は日頃、心身の体調を崩されている方々に寄り添いながらも日々己の課題に向き合っています。それは『寄り添う』事の本質に向き合う為にはとことんまで、物事の本質に向き合わなければならないからです。そして、その為には相手の心を自分自身の心に写し合わせて、自分ならどうするか?自分なら余命何日という宣告をされたらどう考えるか?等突き詰めて考えているからです。そんな事できる訳がない!というご批判が当然の様に出てきそうですね。私もかつてはそうでした。自分自身の課題に向き合おうとせず、自分自身の課題に対して周囲を気にし過ぎて、その評価を気にしたり、批判ばかりして、正面から向き合おうとしない言い訳を考えてばかりでした。それでは相手の課題を考える資格はないのは当然です。その様な致命的な自らの欠点に…いつの頃からか気付きました。
ではどうすれば良いか?
自らの課題を素直に認めて、その課題に取り組めば良いだけです。ボランティアに取り組んでいる事もその1つの方法論です。でも、その為に自らを追い込んでしまう事もあります。その重圧に耐える為にどの様にすれば良いか?
8月は…そんな、全ての頑張っている方々にピッタリな季節ではないでしょうか?
秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ
わが衣手は 露にぬれつつ
万葉集という、古典にふれながら、「葉月」という言葉に耳を澄ませると、現代の私たちも、季節のうつろいにそっと心を寄せたくなるかもしれませんね。
1年の折り返し地点に来た『今』だからこそ、少し大きく深呼吸をしながら、暑い毎日ではありますが、1年の最初に皆様が心に誓った目標に向けて、今一度飛躍のジャンプをする心構えを新たにして参りたいですね。
そんな目標に皆様が届く事ができます様に…陰ながら…これからも応援して参りたいと思います。